郷里の日の暮れは早い。周りを照らす灯りというものが限られているからだろう。
実家の門の前に着いたとき、辺りは真っ暗だった。
都心なら、集合住宅の灯り、街灯の光がそこかしこから、というのが見慣れた光景だが、郷里では一軒家がほとんどで皆夕刻になると雨戸を閉める。ので、部屋の灯りというのもあまり洩れてこない。
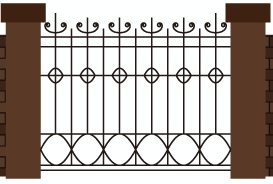
数日前に22日土曜日の夕刻帰るからと便りを送っていたので、いつもと同様に門を開けて待っているはずと、疑わなかった。
が、墓参のため里帰りした私を出迎えたのは、開けようとしても適わない、錠の閉まった鉄の門だった。
合い鍵はある。骨折入院の際、実家での寝泊まりのため、門も玄関も、全ての合い鍵をこしらえており、それを携行している。
鉄格子の向こう側にある錠前にこちら側から合い鍵を差し込もうとするがどうも勝手が悪い。私の近眼とも相まって、鍵穴さえ確かめるのに四苦八苦の状態だ。
都心とは違うとはいえ、ご近所もある、暗闇でそれ以上ガチャガチャ人知れずやっていると、気がつけば後ろにお巡りさん、とならぬとも限らない。
いや、そんなことより私の体中を包み込んだいやぁ〜な感覚、もしや、私の帰省予定が文字で伝えても遂に忘れ去られてしまったか、という不安の方が明らかに大きかったことに間違いはない。
それでは、と門の外から電話してみる。右側で鳴る呼び出し音をそのままに、左側で、「あなた誰?なんて言われる日が来るのかな」などと思いをめぐらせる。

「もしもし、私だけど、門の外にいるんだけど・・・。」

「あっ、そうなの。ちょっと待って、今お風呂から出たばかりなので。」

「それなら急ぐことはないよ。5分ほどしたら出直すから。」
そろそろどうかな、と二度目の電話をすることもなく程なく玄関から母が姿を現し、門が開けられた。

「いや、明日来るものとばかり思ってた。」

「手紙は届いてる?」

「もちろん。」
などと言葉を交わせ居間へ。
甘い物に目がない母に、買い揃えた土産を手渡す。はたして、そういう物が健康上、認知症患者にとって、医学的にどうなのか、(実のところよくはない、と思っている)と意識しながらも、そういう一時のささやかな幸せを味わう権利を他人の一存で奪い去るという決断もこれまでの私にはし難いこと。

「まぁまぁ、これは、いつもわるいねぇ、さっそく父さんの仏檀に供えましょうかねぇ。」
とすでに供物でいっぱいになったかに見える仏前に強引に土産物を押し込む母。
続く四方山話の最中、私の帰省予定日の件に話が及ぶ。

「手紙に、22日土曜日夕刻と書いたけど、手紙はまだ持ってる?」

「持ってるよ。今日は21日だから明日帰ってくると思ってたんだよ。」

「今日は22日だよ。」

「そう?」
と、傍らに置いた新聞紙を手に取る。

「えぇと・・・。21日になってるよ。」
と、重ねた新聞紙のもう片方に目を移す。

「あっ、22日だ。そうかぁ。」
あぁ、そういうことね。忘れた云々でなく、参照元自体を取り違えていたと。少々安堵。
それでも、「今日は22日(土)だよ→いや21日(金)じゃない?→新聞見る→あっ22日だ」の会話がその夕刻に何度か続いたことはいつも通り。